夜寝ている間に気付かないうちにしている歯ぎしりをしていませんか?
実はこの習慣が、顎のズレや歯並びの乱れといった問題につながることがあります。
特に受け口(反対咬合)との関連が指摘されることもあり、将来的な口腔トラブルを防ぐためにも早期の理解と対策が必要です。
本記事では、歯ぎしりと受け口の関係を中心に歯ぎしりの原因や治療法、セルフチェック法などをわかりやすく解説します。
受け口と歯ぎしりの関係
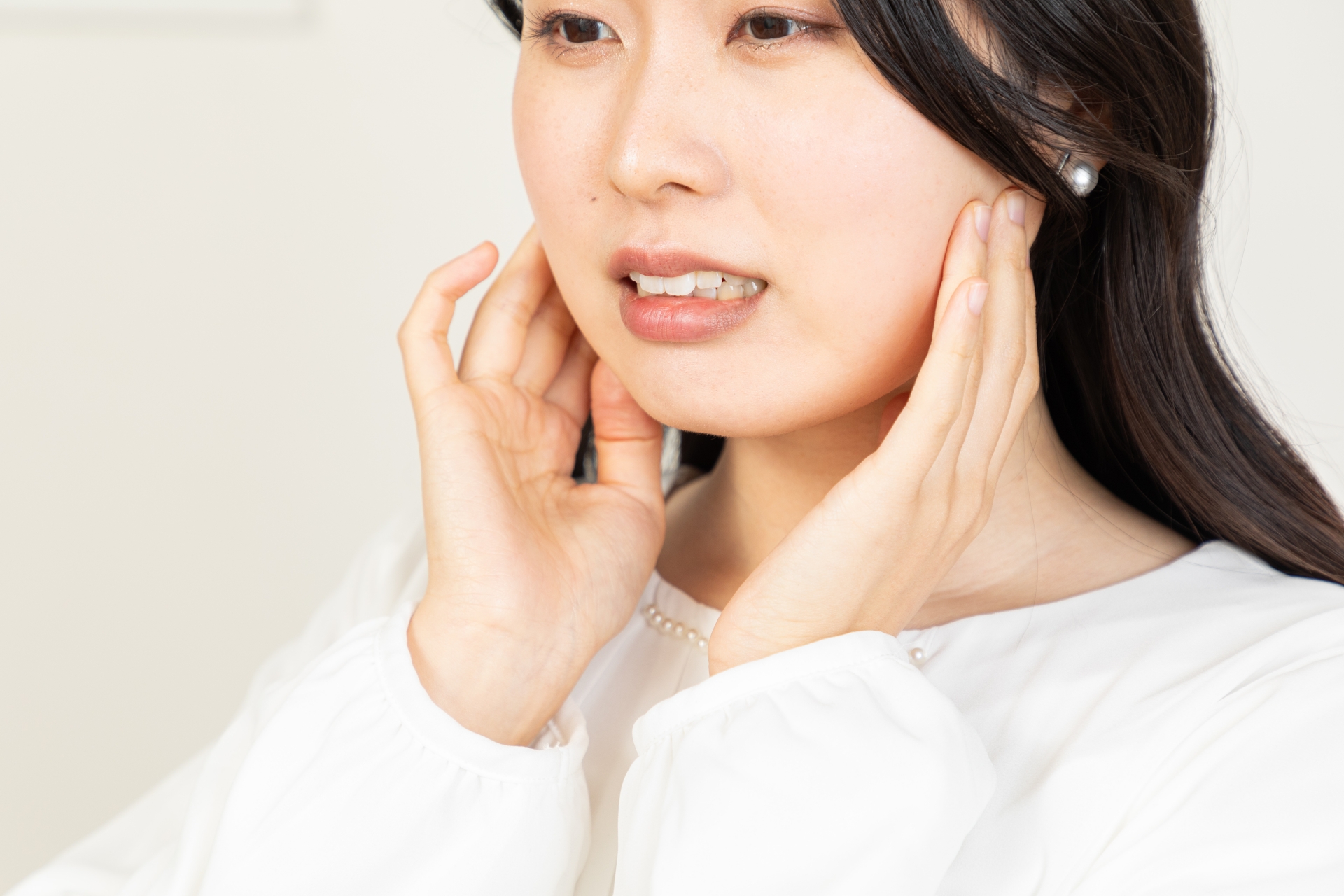
- 受け口はどのような状態のことですか?
- 受け口(反対咬合)とは、下の前歯や下顎が上の前歯より前に出ている噛み合わせの状態のことです。通常は上の歯が下の歯にわずかに被さる形が理想的ですが、受け口ではその関係が逆転しており、見た目に違和感を与えます。また口元が突出して見えたり、お顔全体のバランスに影響を与えたりすることもあります。発音や咀嚼機能への支障も報告されており、サ行やタ行の発音が不明瞭になったり、前歯で物が噛みにくくなるケースも少なくありません。
- 受け口になる原因を教えてください。
- 受け口は見た目の問題ではなく、咬合や骨格、日常生活の習慣とも深く関わっています。発症の背景にはさまざまな要因が複雑に絡み合っており、ひとつの原因に限定できないのが特徴です。特に小児期は、顎の成長が活発であるため、環境や行動によって受け口のリスクが高まることがあります。受け口の原因は、大きく分けて次の3つに分られます。
- 遺伝的な骨格要因:両親のどちらかが受け口の場合、子どもに遺伝することがある
- 幼少期の癖:舌を前に出す、頬杖をつく、口呼吸など
- 歯並びや噛み癖の影響:偏った咀嚼や、歯ぎしりによる歯列のズレ
これらの要因は、単独で影響するだけでなく、複数が重なることで受け口を悪化させるケースもあります。遺伝的に下顎が発達しやすい体質に加え、頬杖や舌癖などの習慣があると、より明確な受け口になっていく可能性が高いです。成長期の子どもにおいて、日常の癖が骨格や歯列の発達に大きな影響を与えることがあります。
- 歯ぎしりの癖があると受け口になりやすいですか?
- 歯ぎしりの癖が続くことで、間接的に受け口(反対咬合)のような噛み合わせのズレを引き起こす可能性があります。特に問題となるのは、就寝中の強い食いしばりや横方向の歯のこすれが慢性的に繰り返されるケースです。歯ぎしりの習慣があると、下の歯が上の歯に対して強い圧力をかけ続けることになります。その結果、歯の位置や傾きが徐々に変化し、下の前歯が前方に押し出されるような状態になりやすいです。長期間の歯ぎしりによって、上下の歯の噛み合わせバランスが崩れることで、下顎が前方に突き出しやすくなる可能性もあります。
歯ぎしりの原因と影響

- 歯ぎしりにはどのような種類がありますか?
- 歯ぎしりといっても、動き方や力の入れ方によって種類が異なります。それぞれのタイプには特徴があり、影響を受ける部位や治療のアプローチも違います。自分がどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切な対策や予防につながる第一歩です。
- グラインディング(歯をこすり合わせる):もっとも一般的なタイプで、歯を横にギリギリとすり合わせ、音が出やすいのが特徴
- クレンチング(歯を強く食いしばる):上下の歯を強く噛みしめるタイプで、音はあまり出ませんが、顎の筋肉や関節に大きな負担がかかる
- タッピング(歯をカチカチと打ち鳴らす):上下の歯を小刻みに打ち鳴らす動きで、神経的な緊張と関連することがある
いずれも、本人が気付かないうちに行っていることが多いです。就寝中に起こることが多いため、家族やパートナーからの指摘で初めて気付くケースがほとんどです。歯ぎしりの種類を把握することが、的確な対応策につながります。
- 歯ぎしりの原因を教えてください。
- 歯ぎしりはひとつの原因で起こるわけではなく、いくつかの身体的や精神的、生活習慣的な要因が複雑に絡み合って発生することが多い症状です。なかには、生活環境の変化やストレスによって急に歯ぎしりが始まったというケースも珍しくありません。歯ぎしりの原因として考えられている代表的な要因は、以下のとおりです。
- ストレスや精神的緊張:仕事や人間関係、試験前など
- 睡眠の質の低下:睡眠時無呼吸症候群や浅い眠りが続く場合
- 噛み合わせの不調:上下の歯がうまく接触していない
- アルコールやカフェインの過剰摂取:寝つきの悪化や中途覚醒との関連
現代では、精神的なストレスや緊張が大きなトリガーとなって歯ぎしりを引き起こすケースが増えています。なかでも日中の緊張が、寝ている間に歯ぎしりという形で現れるというパターンが多く、就寝中のため気付きにくい分、注意が必要です。
- 歯ぎしりの癖があると身体にどのような影響がありますか?
- 歯ぎしりは単なる口腔の問題にとどまらず、頭部や首、肩、さらには精神面にまで影響を及ぼす全身的なトラブルの要因になり得ます。力の加わり方や歯ぎしりの頻度によっては、長期間かけて身体にさまざまな不調が積み重なっていく可能性があります。歯ぎしりを放置すると、以下のような症状や障害が起きることがあるので注意が必要です。
- 歯のすり減りや破損
- 顎関節症:お口を開けづらい、カクカク音がするなど
- 肩こりや頭痛、顔面痛などの筋肉緊張症状
- 噛み合わせの悪化や顔貌変化:エラのハリや非対称
また、歯ぎしりが原因で発生する頭痛や肩こりが慢性化すると、集中力の低下や日常生活でのパフォーマンスの低下にもつながります。
- 歯ぎしりのセルフチェック方法を教えてください。
- 歯ぎしりは自覚症状がほとんどないといわれているため、自分は問題ないと考えている方でも、実は長年にわたって歯ぎしりを続けていたということもあります。放置してしまうと、気付いたときには歯や顎に大きなダメージが及んでいることもあるため、セルフチェックで早期の発見を目指すことが大切です。以下の項目に心あたりがある場合、歯ぎしりの可能性があります。
- 朝起きたときに顎が疲れている、痛い
- 就寝中に家族から歯ぎしりの音がうるさいと言われた
- 歯の表面が平らになってきた、またはヒビが入っている
- 話すときや食事中に顎が鳴る、違和感がある
複数の項目に該当する場合は、できるだけ早く歯科医院を受診しましょう。歯科医院では、歯の摩耗状態や噛み合わせ、顎の状態を確認してもらえます。
歯ぎしりの対策と受け口の治療方法

- 歯ぎしりの対策方法はありますか?
- 歯ぎしりを根本的に治すことは簡単ではありませんが、日常生活に取り入れられる予防策や緩和方法はあります。就寝中に無意識で行われるケースが多いため、意識的な対策と受動的に守る手段を組み合わせることが大切です。歯ぎしりを改善するための対策には、以下のような方法があります。
- マウスピースの装着
- 睡眠の質を高める生活習慣の見直し
- ストレスの軽減(カウンセリングやリラクゼーション)
- 噛み合わせの調整(必要に応じて歯科治療)
これらの対策は、すぐに効果が表れるわけではありませんが、継続的に取り入れることで歯や顎へのダメージを軽減し、症状の悪化を防ぐことができます。 マウスピースは歯ぎしりによるすり減りや歯の破折から守る役割を果たすため、歯科医院で自分に合ったタイプを処方してもらうと安心感を持てます。
- 受け口の治療方法を教えてください。
- 受け口の治療は、症状の原因や年齢、骨格の状態によって治療法が大きく異なります。軽度のケースでは歯列矯正だけで改善できる場合もありますが、骨格的な問題がある場合は、外科的な処置が必要です。受け口の治療には、原因や年齢に応じて以下のような方法が検討されます。
- 子どもの場合:成長期を利用した機能的矯正装置や上顎の拡大装置など
- 成人の場合:ブラケット矯正
- 重度の場合:外科的矯正(顎の骨を整える手術と矯正の併用)
小児期の受け口は、骨の成長をコントロールできる時期に治療を開始することで、将来的に大きな治療を避けられる可能性が高まります。一方で、大人になってから受け口が気になり始めた方も、歯列矯正を活用することで見た目の改善や咀嚼機能の向上が可能です。治療法の選択には医師の判断が必要となるため、自己判断せず歯科医師による精密な診断を受けることが大切です。
- 歯ぎしりは歯列矯正で改善されますか?
- 歯ぎしりの原因が噛み合わせや歯列の不調にある場合、歯列矯正によって咬合バランスを整えることが、歯ぎしりの軽減につながりやすいです。特に、上下の歯の接触ポイントがずれている場合、それが脳に不快な位置として認識され、無意識の食いしばりやすり合わせを誘発していることもあります。歯列矯正治療によって上下の噛み合わせが正しくなったことで、夜間の歯ぎしりが自然と減少したという症例も報告されています。前歯が深く被っていたり、奥歯の咬合が安定していなかったりするケースでは、改善の効果が高いです。歯ぎしりはストレスや睡眠の質といった心理的、生活習慣的な要因が大きく関与している場合も多いです。そのため、歯列矯正を行ったからといって、完全に治るとは限りません。
編集部まとめ

歯ぎしりと受け口には、想像以上に深い関係性があります。
長期間放置してしまうと、噛み合わせがずれたり下顎が前方に押し出されたりすることで、後天的に受け口のような状態になってしまう可能性も否定できません。
また、歯ぎしり自体も歯や顎にダメージを与えるだけでなく、頭痛や肩こり、不眠などの全身症状に発展することもあります。
無意識に続く歯ぎしりは、知らず知らずのうちに生活の質を下げているかもしれません。 歯ぎしりや受け口の対策には、マウスピースや生活習慣の改善、歯列矯正、早期の診断などできることがたくさんあります。
特に成長期の子どもは骨格が変化しやすいため、気になるかもと感じた段階での相談が、その後の治療負担を大きく減らせます。
参考文献
