近年、歯列矯正を快適に受けられるという触れ込みから、マウスピース型矯正を始める人が急速に増えています。歯列矯正に関しては、マウスピース型矯正のみに対応している歯科医院も少なくありません。 しかし、マウスピース型矯正を始めてみたものの、「思っていたのとは違う」「マウスピースの装着時間が守れない」などの理由から、途中で矯正治療をやめるケースも増加しています。この記事では、マウスピース型矯正を中断するケースやデメリット、再開する場合の注意点などを詳しく解説します。
マウスピース型矯正を中断する主なケース
 マウスピース型矯正を途中でやめたい、あるいは実際に途中でやめたケースについて解説します。
マウスピース型矯正を途中でやめたい、あるいは実際に途中でやめたケースについて解説します。
装着時に痛みや違和感を覚える場合
マウスピース型矯正の装置は、透明な樹脂で作られており、一見すると何もつけていないように見えるのが特徴です。ワイヤー矯正の装置よりも、装着感も良好と感じるのが一般的です。
しかし、実際にマウスピース型矯正を始めてみると、マウスピースを装着したときの痛みや違和感、異物感に耐えられなくなってしまうケースもあります。マウスピース型矯正は患者さんが想像していたより、痛かったり、異物感を感じてしまいます。
インターネットやSNSでは、マウスピース型矯正の装着感がよい面や痛みが少ないという利点が強調されているため、現実とのギャップを感じて途中でやめたいと思う方もいます。
むし歯や歯周病がある場合
マウスピース型矯正は、ワイヤー矯正よりもむし歯や歯周病にはなりにくい歯列矯正の方法です。マウスピース型矯正では、食事と歯磨きの際に矯正装置を取り外せることが理由です。
ただし注意点として、マウスピースをつけたままで口にできるのは、水のみです。無糖の炭酸水であっても酸性度が高いため、マウスピースを装着したまま飲むのは避けましょう。ワイヤー矯正なら装置をつけたまま何でも口にできるのですが、マウスピース型矯正の場合は、水か炭酸水に限定されます。少しくらいならジュースやワインを飲んでも大丈夫だろうと考えていると、マウスピースと歯との間に飲料が堆積し、むし歯リスクを高めてしまいます。
また、マウスピース型矯正では歯の表面にアタッチメントと呼ばれる突起物を設置することが一般的で、アタッチメントの周りにも食べカスや歯垢がたまりやすくなります。 マウスピース型矯正には、このようなデメリットもあり、軽視していると、むし歯や歯周病にもつながってしまいかねません。むし歯や歯周病を発症すると、場合によっては治療計画の見直しやマウスピースの作り直しが必要になることがあります。ただし、軽度の場合は矯正を継続しながら治療することも可能です。まずは歯科医師に相談しましょう。
引越しや転勤などの環境変化
マウスピース型矯正をはじめとした歯列矯正は、歯を動かすのに1年半から3年程度かかるのが一般的です。この期間中に進学や転勤などで引っ越しをするケースも少なくありません。
転居先が歯科医院に近く、引っ越し後も引き続き通院できれば問題ないのですが、難しい場合はマウスピース型矯正を中断することになります。転居先でマウスピース型矯正の治療を現地の歯科医院に引き継いでもらえるのであれば問題はありません。
ただし、転院できる歯科医院が見つからなかったり、費用が追加で発生するなどの理由から、マウスピース型矯正を途中でやめてしまう方もいます。
正しい着用時間がどうしても難しい場合
マウスピース型矯正のマウスピースは、1日20〜22時間程度の装着が必要です。これが守れないと、歯が計画どおりに動かないどころか、後戻りも起こりやすくなります。 マウスピース型矯正を始める前の人は「20時間なら装着できるだろう」と考えがちですが、食事や歯磨きの時間を除くと、ほぼ1日中マウスピースをつけておかなければならないため、想定するよりも正しい装着時間を守れないケースも出てきます。
マウスピース型矯正の場合は、患者さん自身の意志で装置を自由に取り外せることから、自己管理が苦手な人は装着時間が不足しがちになります。その結果、マウスピース型矯正を中断せざるを得なくなるのです。
妊娠や出産など
妊娠中は、つわりや体調変化などに悩まされることもあり、精神的にも余裕がなくなりやすい時期です。そのようななかで、マウスピース型矯正の自己管理まで行わなければならないのは、想定するよりも難しいものです。
近い将来に妊娠を予定している場合は、マウスピース型矯正は出産後しばらくしてから始めるのが望ましいです。もちろん、妊娠中でも問題なくマウスピース型矯正を続けられる方もいますが、その可否はその環境に身を置いてみなければわからないものなので、「自分ならできる」と過信するのはよくありません。
マウスピース型矯正の中断がもたらすデメリット
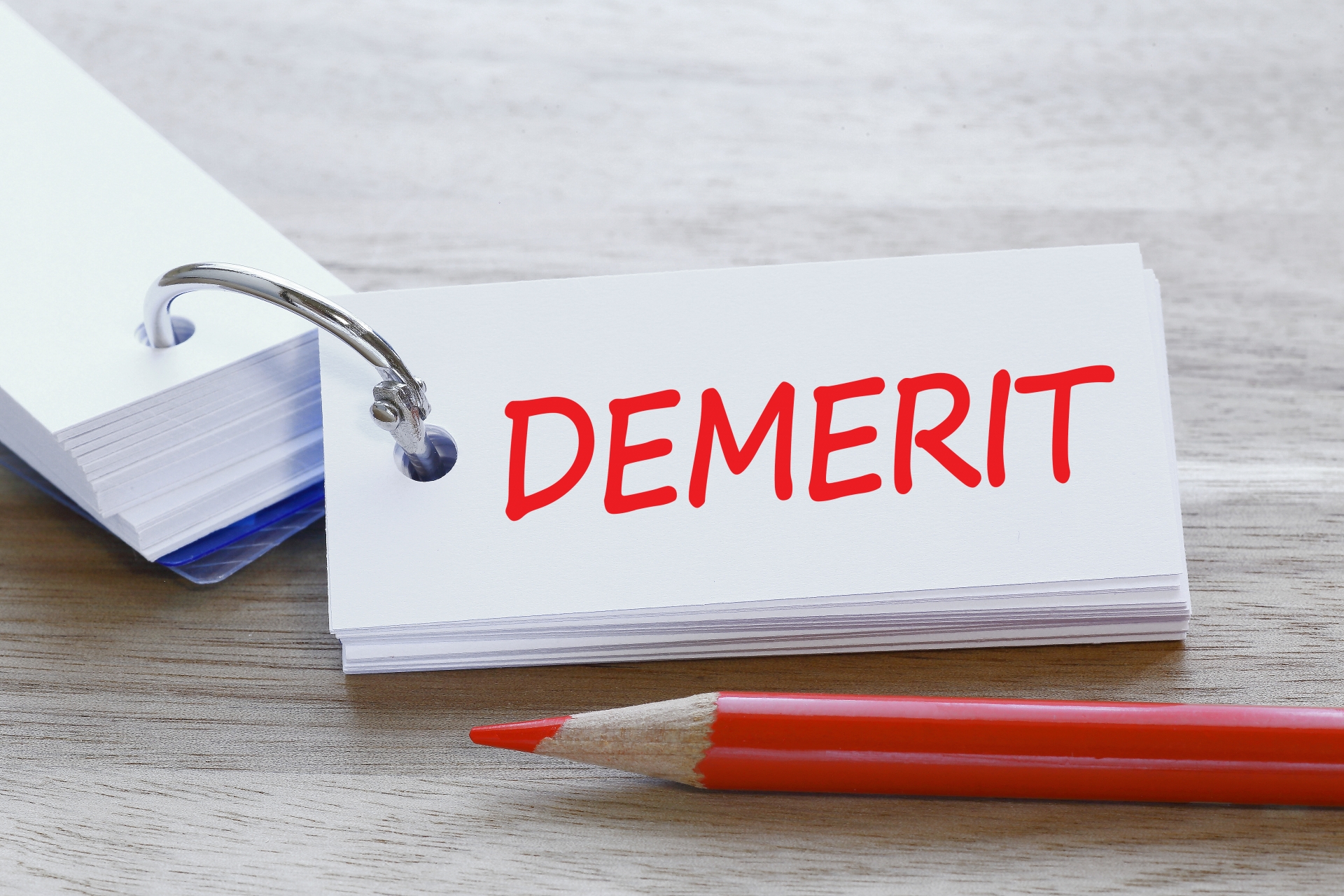 マウスピース型矯正を途中でやめるとどのようなデメリットが生じるのかについて解説します。
マウスピース型矯正を途中でやめるとどのようなデメリットが生じるのかについて解説します。
後戻りするリスクがある
マウスピース型矯正を途中でやめると、ほぼ100%の確率で後戻りが生じます。
これまで時間とお金をかけて動かしてきた歯が元の位置に戻ってしまうのは、患者さんにとっては避けたいところでしょう。歯の後戻りというのは、数年間にわたるマウスピース型矯正が完了して、保定期間に移行してからも起こりうるものです。
治療期間が長期化する
途中でやめてしまうと、治療期間は長期化してしまいます。マウスピース型矯正は、途中でやめても再開することは可能です。
例えば、歯周病やむし歯が原因でマウスピース型矯正を中断した場合は、早ければ数週間、遅くても半年以内には治療を再開できますが、当初の治療期間より長くなります。 マウスピース型矯正を中断した期間だけ延びるのではなく、後戻りや計画の立て直しを伴うことから、より長い期間の延長が必要となります。治療期間が長期化することは、費用が多くかかるだけでなく、患者さんの心身にかかる負担も大きくなります。
歯並びや噛み合わせの悪化
マウスピース型矯正の中断は、歯並びや噛み合わせの悪化につながることがあります。歯列矯正は、必ずしも歯並びや噛み合わせが、日々、改善されていくものではありません。
治療目標に到達するまでの過程では、一時的に歯並びや噛み合わせが悪くなることもあります。もし、そのようなタイミングでマウスピース型矯正を中断すると、治療を始める前より歯並びや噛み合わせが悪くなります。
また、マウスピース型矯正の中断には後戻りを伴うことから、歯並びや噛み合わせが正常な状態で安定することもほぼあり得ません。それだけにマウスピース型矯正を始めとした歯列矯正を途中でやめることは、基本的に推奨できません。
再開時にマウスピースが合わない可能性も
治療を途中でやめてしまうと、使用していたマウスピースが合わなくなってしまうこともあります。
近い将来に再開することを前提として、マウスピース型矯正を中断するのであれば、大きなリスクやデメリットを伴わないだろうと考える方もいます。マウスピース型矯正を中断している期間が数日程度であれば、リスクやデメリットはほぼないといえますが、中断する期間が1週間を超える場合は、再開時にマウスピースが合わない可能性が出てきます。
これは歯列の後戻りが原因です。後戻りは、むし歯治療でマウスピース型矯正の中断が1〜2週間で済んだとしても、合わなくなってしまうことがあります。その期間が数ヵ月になれば、治療計画の立て直しが必要になるかもしれません。
費用が無駄になってしまう
マウスピース型矯正を途中でやめることは、それまで支払った費用が無駄になる可能性が高いです。
マウスピース型矯正を中断する時期によっても結果は変わりますが、再開することを前提していないのであれば、歯並びや噛み合わせが元の状態へと戻ります。
マウスピース型矯正の再開を前提とした場合であったとしても、マウスピースの作り直しや治療計画の立て直しによって新たな費用がかかるため、経済的な損失は避けられません。
マウスピース型矯正を途中でやめる場合は歯科医師に相談
 マウスピース型矯正を途中でやめると、患者さんにたくさんのデメリットがあるため、安易に中断するのはおすすめできません。
マウスピース型矯正を途中でやめると、患者さんにたくさんのデメリットがあるため、安易に中断するのはおすすめできません。
まずは、マウスピース型矯正を途中でやめることを歯科医師に相談することが大切です。マウスピース型矯正を途中でやめると、どのようなリスクがあるのかよく確認しましょう。
マウスピース型矯正を受けている歯科医院であれば、治療内容や治療経過を把握しているので、途中でやめた場合のリスクやデメリットも明確に提示してくれます。また、マウスピース型矯正の状況によっては、今の状態を保存したまま治療を中断することも可能かもしれません。
このような点も考慮して、マウスピース型矯正の中断を検討する場合は、自己判断せずに専門家の意見を求めることが大切です。
再開する際のポイント
 中断したマウスピース型矯正を再開する場合のポイントを紹介します。
中断したマウスピース型矯正を再開する場合のポイントを紹介します。
新たな治療目標の設定とモチベーション維持の工夫
マウスピースの装着時間が守れなかったり、装置による痛みや違和感に悩まされたりして、マウスピース型矯正を中断した方は、再治療のときには、目標の設定とモチベーション維持の工夫が必要となります。
中断する前と同じような状態で再開しても、結局、治療を中断してしまうということにもなりかねません。具体的には「きれいな歯並びを手に入れて、笑顔に自信を持てるようにする」という抽象的な動機付けでもよいですし「1年後には矯正治療を終わらせる」といった具体的な目標を設定してもよいでしょう。
定期診察などでフォローアップを受ける
マウスピース型矯正は、定期的な通院をしなくても治療を進められるケースがありますが、基本は歯科医師の指示どおりにフォローアップを受けましょう。
主治医からアドバイスをもらったり、矯正で悩んでいることを聞いてもらったりすることでも、治療へのモチベーション維持につながります。マウスピースの装着時間の不足や装着方法の誤りなどを指摘してもらえるため、マウスピース型矯正を再開するうえで定期診察は欠かすことができません。
十分な準備と体調管理を行う
妊娠・出産、お口の病気などでマウスピース型矯正を中断したケースでは、再開する際に十分な準備が必要となります。
また、体調管理も万全にした状態でなければ、再開してもすぐにまた中断する可能性が高まるため要注意です。
別の矯正歯科を紹介してもらう
引っ越しによってマウスピース型矯正を中断したケースでは、別の矯正歯科への転院が必要となります。
その際には、転居前の主治医に相談して紹介状の作成をお願いしましょう。転院先でまったく同じマウスピース型矯正を採用している場合は、引き継ぎを行えることもありますが、基本的には主治医に紹介状と診療情報提供書を作成してもらう必要があります。
また、転居先に主治医との交流がある矯正歯科があれば、そこを紹介してもらうのもよいでしょう。
マウスピース型矯正を途中でやめた場合の代替案
 マウスピース型矯正の装着時間が守れなかったり、飲食の際に不便を感じたりすることが原因で治療を中断した場合の代替案を紹介します。基本的には、表側矯正と裏側矯正(舌側矯正)の2つの選択肢が用意されています。
マウスピース型矯正の装着時間が守れなかったり、飲食の際に不便を感じたりすることが原因で治療を中断した場合の代替案を紹介します。基本的には、表側矯正と裏側矯正(舌側矯正)の2つの選択肢が用意されています。
表側矯正
歯列の表側にブラケットとワイヤーを固定する治療法です。
装置の装着は歯科医師が行い、患者さんが自己管理することはほとんどありません。装置を装着した状態で食べ物や飲み物を口にできる点もマウスピース型矯正と大きく異なります。
裏側矯正(舌側矯正)
歯列の裏側にブラケットやワイヤーを固定する治療法です。
基本的な特徴は表側矯正と同じで、審美面においてはマウスピース型矯正よりも優れています。そのため自己管理する範囲が少なく、見た目も自然な矯正法を希望する場合は、裏側矯正(舌側矯正)が適しているといえます。
まとめ
今回は、マウスピース型矯正を途中でやめるケースや中断するデメリット、再開する際の注意点について解説しました。
マウスピース型矯正を途中でやめるケースとしては、装着時の痛み、むし歯や歯周病の発症、引っ越しによる環境の変化、マウスピースの装着時間が守れないなどが挙げられます。こうした理由からマウスピース型矯正を途中でやめるとさまざまなデメリットを伴うことから、中断を決める前に歯科医師と話し合うことが大切です。
中断したマウスピース型矯正を再開することも可能ですが、その際には本文でも解説したポイントに注意しましょう。
参考文献
