歯列矯正が成功して、きれいな歯並びが手に入ったのに、しばらくしてから出っ歯になった。こうしたケースは珍しくありません。歯列矯正後の保定や生活習慣、通院の状況によって、歯の後戻りが生じるからです。
この記事では、歯列矯正後に出っ歯になった原因や改善策、再矯正の必要性を解説します。歯列矯正後の出っ歯で悩まされている方は、参考にしてみてください。
歯列矯正後に出っ歯になった原因
 歯列矯正後に出っ歯になる主な原因としては、歯の後戻りと悪習癖の2つが挙げられます。
歯列矯正後に出っ歯になる主な原因としては、歯の後戻りと悪習癖の2つが挙げられます。
【原因1】歯の後戻り
歯列矯正が成功して、歯並びがきれいになったにも関わらず、しばらくしてから出っ歯になった場合は、歯の後戻りが起こった可能性が高いです。
歯列矯正では、マルチブラケット装置やマウスピース型矯正装置を使って歯を物理的に動かしますが、治療直後は元の状態に戻ろうとする力が強く働きます。そのため歯列矯正後の保定処置を怠っていると、歯の後戻りが起こって出っ歯になってしまいます。
もともとの出っ歯ではなくても、非抜歯で無理に矯正した場合、スペースが不足することで前歯が歯列の外側へと逸脱して、出っ歯の症状が現れることもあります。
【原因2】悪習癖・悪習慣
歯列矯正後の悪習慣が原因で、出っ歯になってしまうことがあります。具体的には以下の習慣がある方は注意です。
・口呼吸
・舌で前歯を押しだす癖
・爪を噛む癖
・歯ぎしり、食いしばり
・片側だけで噛む癖
・頬杖をつく癖
特に、口呼吸や爪を噛む癖、舌で前歯を押しだす癖は、歯列矯正後の出っ歯を引き起こしやすいとされています。
歯列矯正中は装置が支えとなって影響を緩和できるのですが、装置を撤去した後は歯に対して直接力がかかるようになります。前歯を前方へと傾ける原動力となってしまいます。
歯列矯正後に出っ歯を防ぐための対策
 歯列矯正後の出っ歯を予防するための対策方法を解説します。もうすぐ歯列矯正が終わる方や終わったばかりの方は、以下の3つの対策を徹底して、出っ歯になるのを防ぎましょう。
歯列矯正後の出っ歯を予防するための対策方法を解説します。もうすぐ歯列矯正が終わる方や終わったばかりの方は、以下の3つの対策を徹底して、出っ歯になるのを防ぎましょう。
保定装置を歯科医師の指示どおりに使用する
歯列矯正後の出っ歯を防ぐために大切なのは、保定装置を指示どおりに使用することです。
◎そもそも保定とは?
歯列矯正は、歯を動かす動的治療と歯の位置を固定する保定処置の2つに分けられます。
動的治療だけで歯列矯正が完結することはなく、保定処置を行わないとほぼ100%の確率で後戻りが生じます。これは歯と顎の骨をつなぎとめている歯周靭帯が一定期間、もとの位置にとどまり続けるからです。
歯を動かした後に保定装置を装着して、数ヵ月から数年経過すると、歯周靭帯も歯列矯正後の位置へと移動していきます。こうした歯周組織のリモデリングが完了するまでは、保定を継続する必要があります。
◎保定装置の正しい使い方
保定装置は、固定式と着脱式の2種類があります。
固定式は歯科医院で装着するため、患者さんが着脱することはありません。日頃のケアをしっかり行いましょう。
着脱式は患者さんが毎日着けたり外したりするため、使用方法には注意がいります。以下の保定期間を想定してください。
・保定開始から1年間は1日20時間
・1年以降、毎日12時間程度
・2年間は、毎日夜間8時間程度
・3年以降、2日ごとに夜間8時間程度
・4年以降、週2回夜間8時間程度
・5年以降、週1回夜間8時間程度
これらは目安で、歯列矯正の状態によって異なります。実際の装着時間は主治医の指示を優先しましょう。
保定装置の装着時間が目安よりも下回ると、出っ歯などの後戻りの症状が起こりやすくなります。また、保定装置の装着方法やお手入れ方法も主治医の指示に従う必要があります。
保定装置の使い方でわからないことや不安に感じることがあったら、自分で解決するのではなく、主治医への相談が大切です。
生活習慣や癖に注意する
歯並びに悪影響を与える生活習慣や癖は、早めに改善するよう努めましょう。保定が始まってから改善したのでは手遅れとなることもあるため、悪習慣・悪習癖は歯列矯正前、もしくは歯列矯正中には改善が望ましいです。
生活習慣や癖は自覚しにくいため、周りの人に指摘してもらうことも大切です。普段から家族や友人などに口呼吸、舌で前歯を押しだす癖、爪を噛む癖、歯ぎしり、食いしばりなどをしていないか確認しましょう。
定期的に通院しチェックしてもらう
歯を動かす動的治療が終わった後も歯科医院への定期的な通院は必要です。通院する間隔は歯科医師の指示にしたがってください。保定期間に入った後の定期的な通院では、以下のチェックを受けます。
◎歯の後戻り
歯の後戻りが起こっていないかをチェックしてもらえます。歯の後戻りが確認された場合は、早期に対処できるため、歯科医院での定期的なチェックは、歯列矯正後の出っ歯などを防ぐうえで極めて重要といえます。
◎保定装置の使用状況
歯列矯正後の定期的な通院では、保定装置を正しく使えているかの確認があります。保定装置を正しい位置に装着できているかどうか、装着時間やケアの状態なども細かく見てもらえるでしょう。
◎悪習癖の有無
歯ぎしり・食いしばりがある場合は、歯に摩耗が見られたり、歯質が部分的に欠けたりすることがあります。その他、歯の後戻りを助長する習癖・習慣がないかも確認してもらうことで、歯列矯正後に出っ歯になる症状を予防しやすくなるでしょう。
歯列矯正後に出っ歯になってしまった場合の対処方法
 もうすでに歯列矯正後の出っ歯の症状が現れてしまった場合は、次の方法で対処することになります。
もうすでに歯列矯正後の出っ歯の症状が現れてしまった場合は、次の方法で対処することになります。
リテーナーで保定する
軽度であれば、保定装置であるリテーナーをしっかりと装着することで改善が見込めます。リテーナーを決められた位置で装着して時間も守れば、徐々に歯列矯正後の歯並びへと改善します。
出っ歯の症状が現れたのは、リテーナーの装着を正しく行えていない可能性が高いです。これまでと同じように保定をしていたのでは不十分かもしれません。後戻りが生じて出っ歯になっている場合は、それよりも長い時間装着することを意識して、保定に臨むようにしましょう。食事と歯磨き以外の時間は1秒でも早くリテーナーを装着するよう心がけてください。
◎リテーナーが壊れた場合は?
装着時間を守っているにも関わらず、出っ歯などの後戻りが生じた場合は、装置トラブルの可能性も考えられます。 例えば、リテーナーのワイヤーが曲がっていたり、熱による刺激で変形したりすることがあります。このような場合は、リテーナーの調整や作り直すことで、歯列矯正後の出っ歯の症状をリカバリーできます。
再矯正治療を受ける
中等度から重度でリテーナーの装着だけではリカバリーできない場合は、再矯正治療を受けることになります。
ワイヤー矯正の場合は、再びブラケットとワイヤーを固定して治療します。マウスピース型矯正の場合は、マウスピースを作り直して装着し、出っ歯の症状を徐々に改善していきます。
再矯正治療は、いわゆる部分矯正のようなものなので、これまで行ってきた全体矯正程長い期間はかかりません。出っ歯を治す費用も安くすむことも少なくありません。
再矯正を受ける場合の注意点
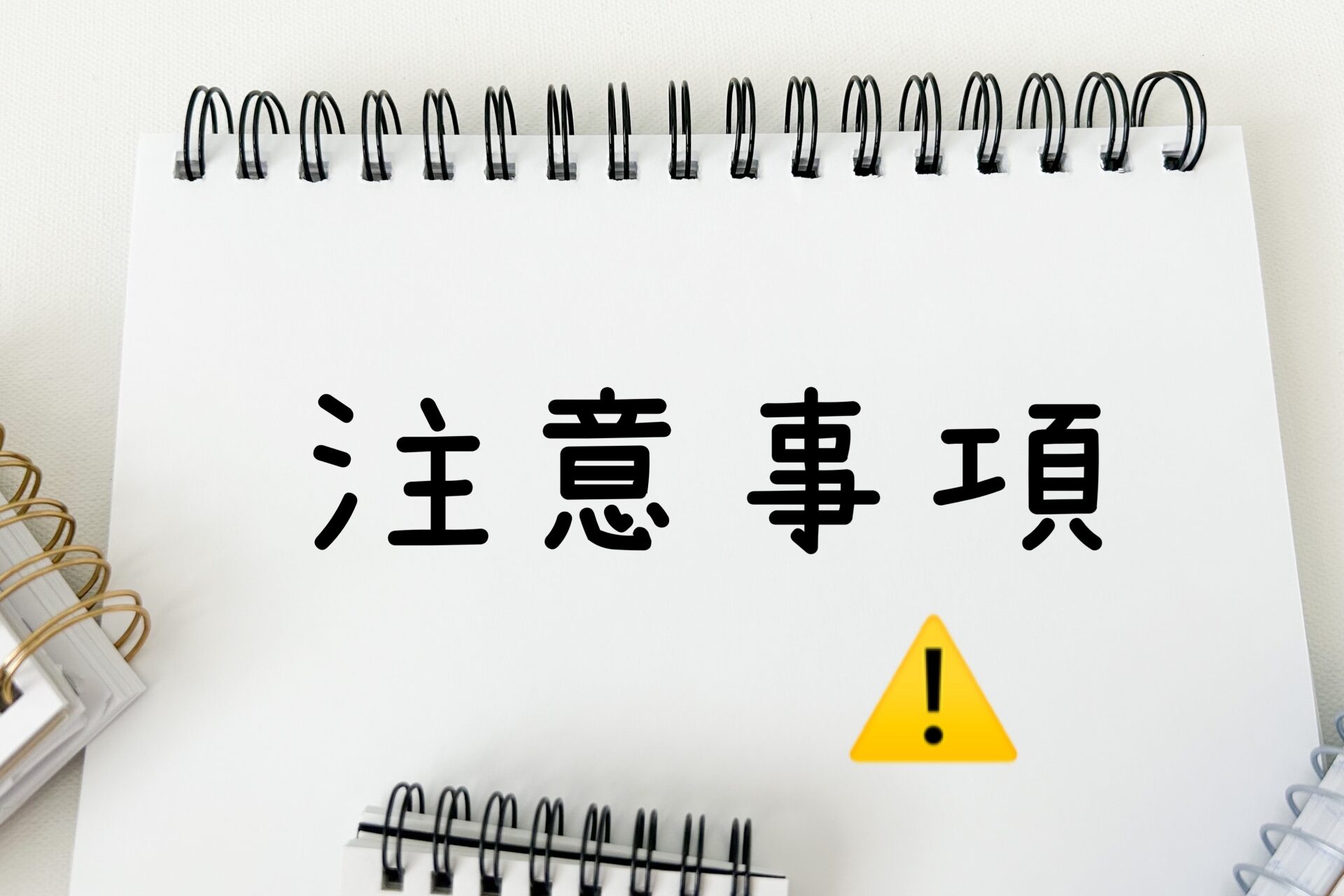 歯列矯正後の出っ歯を治すための再矯正について、注意すべき3つの点を紹介します。
歯列矯正後の出っ歯を治すための再矯正について、注意すべき3つの点を紹介します。
再矯正に伴うリスクを確認する
歯列矯正後の出っ歯を改善する再矯正では、以下に挙げる2つのリスクを伴います。
【リスク1】歯根吸収
再矯正では歯に対して負担がかかるため、歯根が短くなってしまう歯根吸収のリスクが生じます。これは通常の歯列矯正でも起こりうるトラブルですが、ほとんどの場合で許容範囲内にとどまることが一般的です。
【リスク2】歯周病やむし歯になる
再び矯正装置を装着すると、清掃性が悪くなり歯周病やむし歯になるリスクが高まります。基本的には通常の歯列矯正と同じです。
◎再矯正の注意点 再矯正では、次に挙げる2点にも注意が必要です。
【注意点1】追加の費用がかかる
再矯正を行う場合は、一般的に追加の費用が発生します。具体的な費用は、出っ歯の症状や歯科医院の料金設定、保証の内容によって変わります。
また、再矯正を同じ歯科医院で受ける場合は、追加費用を抑えられる可能性があります。患者さんのお口や骨格、これまでの治療経過などの情報がすべてそろっているため、治療方針が決めやすいからです。
歯科医院によっては再矯正の費用は調整料のみの請求で、装置の製作費などは必要としないところもあります。
一方、歯科医院を変えて再矯正を受ける場合は、費用が高額になりがちです。
軽度の症状であっても、精密検査や診断、治療計画の立案などをやり直さなければなりません。これまで通っていた歯科医院からの情報提供があれば、再矯正もスムーズに進めて行くことができますが、基本的には歯列矯正のプロセスをはじめからやり直すことになります。
【注意点2】抜歯が必要になるかもしれない
非抜歯で歯列矯正を行った場合は、治療後の出っ歯の症状が現れやすくなります。
歯をきれいに並べるためのスペースが不足しているので、同じ矯正治療を行ったとしても、再び出っ歯になる可能性もあります。このような場合は、抜歯が必要になることもありますので、事前に正しく理解しておきましょう。
抜歯をして歯をきれいに並べることができれば、後戻りのリスクも減り、きれいな歯並びを維持しやすくなります。その分、再矯正にかかる期間が長く、費用も高くなることは理解しておきましょう。
後戻りしないように注意する
無事に再矯正が終わって、出っ歯の症状が改善しても油断はできません。
これと同じ状況を数ヵ月前に経験したことを忘れてはいけません。患者さんの保定への取り組みや悪習癖の有無によっては、同じような出っ歯の症状が現れても何ら不思議ではないのです。
そのため再矯正を受ける前には必ず出っ歯などの後戻りが生じた原因を正確に把握しておくことが重要です。
保定装置の取り扱いに誤りがあった場合は、正しく使用できるよう努めましょう。
出っ歯を誘発する悪習慣があった場合は、再矯正を始める前に改善するのが原則となります。口呼吸や舌で前歯を押しだす癖、爪を噛む癖などは患者さん自身が意識することで改善しやすいですが、歯ぎしり、食いしばりを取り除くためにはそれなりの時間と労力を要します。
ほとんどの悪い習慣は、専門の歯科医師に相談して、歯ぎしり・食いしばりの治療も視野に入れた準備が必要です。
◎歯ぎしり・食いしばりの治療とは?
歯ぎしり・食いしばりは、ナイトガードと呼ばれる治療用のマウスピースを装着することで改善が見込めます。スプリント療法と呼ばれるもので、一般的な歯科医院で対応しています。歯ぎしり・食いしばりの改善には数ヵ月かかるため、その期間も頭に入れたうえで再矯正に臨み、歯列矯正後の後戻りを防止していきましょう。
セカンドオピニオンを利用してみる
歯列矯正後の出っ歯の症状は、患者さんに原因がある場合と、歯科医院側に原因がある場合の2つに大きく分けられます。
前者は、患者さんの保定への取り組みや生活習慣を改めることで、再矯正を成功へと導けますが、後者は歯科医院を変えた方がよい場合もあるのです。
そのため後者に該当する方は、再矯正を検討するうえでセカンドオピニオンの利用も重要なポイントとなります。歯科医師に第二の意見を求めて、よりよい再矯正が受けられる方法を模索しましょう。
まとめ
今回は、歯列矯正後に出っ歯の症状が現れる原因と改善策、再矯正の必要性について解説しました。歯列矯正後の保定を正しく行わないと、歯の後戻りが生じて出っ歯になることがあります。口呼吸や歯ぎしり・食いしばりなどの習癖によっても同様の症状が現れる場合があるため注意が必要です。
歯の後戻りで出っ歯になった場合は、リテーナーを装着することでリカバリーできることもありますが、症状が強い場合は再矯正が必要となることから、まずは早急に主治医に相談しましょう。
参考文献
