お子さんの床矯正を検討されている方は、床矯正のデメリットについて気になっているのではないでしょうか。本記事では子どもの床矯正について以下の点を中心にご紹介します。
- 床矯正のメリット・デメリット
- 床矯正が向いている歯並び
- 床矯正の失敗を防ぐために
床矯正のデメリットについて理解するためにもご参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
床矯正とは

床矯正とは、成長期のお子さんの歯並びを整えるために行う歯列矯正治療の一つです。取り外し可能な装置を使用し、顎の骨が成長する力を利用して歯列の幅を広げることで、歯が自然に正しい位置に並ぶスペースを確保します。6歳〜11歳頃に治療を始めるのが理想的とされています。
床矯正の装置には拡大ネジが組み込まれており、これを調整することでゆっくりと歯列を側方に広げていく仕組みになっています。歯列が広がると、内側に傾いている歯を外側に押し出し、歯並びを整えやすくなります。
床矯正のデメリット

成長期のお子さんの歯並びを整える床矯正ですが、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
以下で詳しく解説します。
重度の歯並びの乱れには適応できない
床矯正は、成長期のお子さんの顎の発育を利用しながら、歯が並ぶスペースを確保するための矯正方法ですが、重度の歯並びの乱れには対応できないケースが多くあります。
理由の一つとして、床矯正は顎の骨自体を広げるのではなく、歯を外側に押し出すことで歯列を拡大する仕組みである点が挙げられます。そのため、顎の大きさや位置関係に問題がある場合には、適応が難しくなります。
特に、重度のデコボコ(叢生)、出っ歯(上顎前突)、受け口(下顎前突)などの骨格的な問題が関係している症例では、床矯正だけでは改善が困難であり、結果的にワイヤー矯正(マルチブラケット装置)などの追加治療が必要となることがほとんどとされています。
また、専門的な検査が行われずに安易に床矯正をすすめられた場合、適応でない症例に使用してしまい、かえって歯並びが悪化するリスクもあります。特に、出っ歯の治療には不向きで、歯をさらに前に押し出してしまう可能性があるため注意が必要です。
床矯正がおすすめされるのは軽度な歯並びの乱れに限られるため、重度の症例では医師による適切な矯正治療を受けることが重要です。
適応できるタイミングが限られる
床矯正は、適切なタイミングで開始しなければ効果が実感しづらい矯正治療です。
6歳〜11歳頃の成長期の子どもが対象となりますが、治療を始めるためには前歯4本が永久歯に生え変わっていることが条件とされています。
また、床矯正は永久歯がすべて生えそろう前に行う必要があるため、すでに歯が生えそろってしまった場合には適用が難しくなります。このため、適切な開始時期を見極めることが重要です。
床矯正を検討する際は、早めに歯科医師へ相談し、適切なタイミングで治療を開始できるようにすることが大切です。遅すぎると適応が難しくなる可能性があるため、乳歯から永久歯へ生え変わる時期をしっかりと把握し、計画的に矯正治療を進めることが求められます。
後戻りする可能性がある
床矯正は、成長期の顎の発育を利用して歯列を広げる矯正方法ですが、治療後に後戻りする可能性があるとされています。これは、お口周りの筋肉の使い方や生活習慣が影響するため、装置を外した後に元の状態へ戻ろうとする力が働くためです。
また、床矯正は取り外しが可能な装置であるため、装着時間が不足すると十分な効果が得られず、治療が長引いたり、中途半端な状態で顎の成長が終わってしまうケースもあります。特に、治療終了後に保定装置を使用しないと、歯が元の位置に戻るリスクが高まります。
後戻りを防ぐためには、矯正終了後も保定装置を適切に使用することが重要です。さらに、舌や唇の癖を改善し、正しい噛み合わせを維持することで、長期的に安定した歯並びを保つことができるとされています。
床矯正のメリット

床矯正にはいくつかデメリットがある一方で、メリットも多く存在します。
以下で詳しく解説します。
抜歯せずに治療できる
矯正治療では、歯を並べるためのスペースが不足している場合、抜歯を行うことがあります。しかし、床矯正を用いれば、顎の成長を促しながら歯列を広げ、自然にスペースを確保できるため、抜歯を避けられる可能性が高くなります。 特に、成長期の子どもに適用することで、永久歯が正しい位置に生えやすくなり、将来的な矯正負担を軽減できる点も大きな利点です。
また、健康な歯を残せるため、噛み合わせや歯の寿命にもよい影響を与えます。
精神的・身体的な負担も少なく、外科的な処置を避けたい方にとって、床矯正は有力な選択肢となるでしょう。
取り外しできる
ワイヤー矯正のような固定式の装置では、食事の際に食べ物が詰まりやすく、歯磨きもしづらいため、むし歯のリスクが高まります。しかし、床矯正なら食事中に装置を外せるため、普段どおりに食事を楽しむことができ、歯磨きもいつもどおり行えます。 よって、矯正中でも口腔内を清潔に保ちやすく、むし歯を防ぎやすいとされています。
さらに、スポーツやイベントの際にも装置を外せるため、運動中にお口の中を傷つける心配が少なく、見た目が気になる場面でも安心して過ごせます。 取り外しが可能なことで、日常生活への負担を軽減しながら矯正治療を続けられるのが、床矯正の大きな魅力です。
痛みを感じにくい
矯正治療を検討する際、痛みが気になる方は多いのではないでしょうか。床矯正は、顎の骨を徐々に広げる治療法のため、ワイヤー矯正に比べて痛みが少ないとされています。弱い力でゆっくりと歯列を整えるため、急激な圧力がかかることがなく、強い痛みを感じにくいのが特徴です。
ただし、新しい装置を装着した直後や調整後には、一時的に違和感や軽い痛みを感じることがあります。 しかし、これらの不快感は数日で慣れることがほとんどで、痛みも軽度なものが多い傾向にあります。
さらに、床矯正は取り外しが可能なため、ワイヤー矯正のように常に力がかかり続けることがなく、口腔内の負担も軽減されます。矯正治療の痛みが不安な方にとって、床矯正は快適な選択肢といえるでしょう。
床矯正が向いている歯並び

どのような歯並びが床矯正に向いているのか、以下で詳しく解説します。
軽度の叢生(乱杭歯)
叢生(そうせい)とは、歯が重なり合ってデコボコになっている歯並びのことで、歯列矯正治療が必要となるケースのひとつです。 乱杭歯(らんぐいば)やガチャ歯とも呼ばれ、特に八重歯も叢生の一種に含まれます。
この状態は、顎が小さい、歯が大きい、乳歯の生え替わりの問題や癖・習慣などによって、歯を並べるためのスペースが不足することが原因で起こります。叢生があると、歯が重なり合っている部分にプラーク(歯垢)が溜まりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まります。
床矯正は、顎の成長を促しながら歯列を広げることで、永久歯が正しく生えるためのスペースを確保できるため、叢生の治療に合った方法です。 特に、永久歯が生え始める6歳頃から治療を始めることで、抜歯をせずに歯並びを整えられる可能性が高くなります。
軽度の下顎前突(受け口)
受け口とは、上下の歯の噛み合わせが通常とは逆になり、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態のことを指します。 遺伝や顎の発育バランスの影響を受けやすく、歯並びの問題のなかでも治療や管理が難しいとされています。
受け口のまま放置すると、前歯で食べ物が噛みにくくなるだけでなく、発音が不明瞭になったり、顎関節症のリスクが高まったりする可能性があります。 そのため、3歳以降の早い段階で噛み合わせを整え、筋肉のバランスや悪い癖を改善していくことが大切です。
床矯正は、顎の成長をコントロールしながら歯列を整えることができるため、受け口の治療にも有効とされている方法です。 ただし、骨格的な問題が大きい場合は、外科的な治療が必要になることもあるため、早めに歯科医師に相談することが重要です。
過蓋咬合
過蓋咬合(かがいこうごう)とは、上の前歯の嚙み合わせが深く、お口を閉じたときに下の歯がほとんど見えなくなる状態を指します。 この状態になると、噛む力が低下しやすく、話しづらさや顎関節症のリスクが高まるだけでなく、顔のバランスが崩れることもあります。
過蓋咬合には、歯の位置や傾きの問題によるタイプと、上顎と下顎の骨格バランスの問題によるタイプがあり、成長期に適切な治療を受けないと悪化しやすくなります。
床矯正は、下顎の成長を働きかけながらスペースを広げ、正しい噛み合わせに導く治療法として有効とされています。 専用の装置を使い、徐々に顎を広げることで、歯並びを整えるだけでなく、見た目のバランスも改善できます。特に6歳前後から治療を開始することで、将来的な矯正の負担を軽減できる可能性があります。
床矯正の失敗を防ぐために

床矯正の失敗を防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。以下で詳しく説明していきます。
治療開始のタイミングが重要
床矯正は、乳歯から永久歯に生え変わる時期に開始するのが妥当とされています。 歯が並ぶスペースが不足していると、永久歯が斜めに生えたり、別の位置から生えたりすることがあるため、その兆候が見られたら早めに歯科医院に相談することが重要です。
ただし、成長に伴い自然と歯並びが整うこともあるため、保護者の判断だけで治療を決めるのは難しいのが現実です。床矯正を適切なタイミングで開始するには、矯正専門の歯科医師の診断を受けることが大切です。
また、成長期のピークに治療を行うことで、歯や顎の発育を促し、よりよい矯正結果が期待できます。 逆に、治療の開始が早すぎると効果が不十分になる可能性があるため、慎重な判断が求められます。永久歯の歯並びが気になったら、できるだけ早めに歯科医師の意見を仰ぎましょう。
装着期間を守る
床矯正は取り外しが可能なため、正しい装着時間を守ることが治療成功の鍵となります。1日14時間以上の装着が推奨されていますが、装着時間が不足すると計画どおりに歯が動かず、治療期間が長引いたり、別の矯正方法に切り替えが必要になったりすることがあります。
特に、お子さんの場合は装着を忘れがちになるため、保護者や周囲の大人が装着状況をチェックし、声かけをすることが重要です。 せっかく始めた矯正治療を無駄にしないためにも、装着時間を守る習慣を身につけましょう。適切な使用を続けることで、スムーズに理想の歯並びへと近づくことができるとされています。
治療後の維持管理も重要
床矯正は、治療が終わった後の維持管理(保定)を適切に行うことで、歯並びを安定させ、後戻りを防げます。維持管理が不十分だと、矯正した歯が元の位置に戻ってしまい、再び矯正が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
治療後はリテーナー(保定装置)を1〜3年間装着する場合が多いとされており、矯正装置をつけていた期間と同じだけ保定期間が必要とされています。特に、治療後の最初の6ヶ月間は1日20時間以上の装着が推奨されており、装着時間を守ることが重要です。
また、リテーナーは適切なケアを行い、定期的に歯科医院でチェックを受けることも大切です。正しい維持管理を続けることで、床矯正の効果をしっかりと定着させ、美しい歯並びを長く維持できるようになります。
まとめ
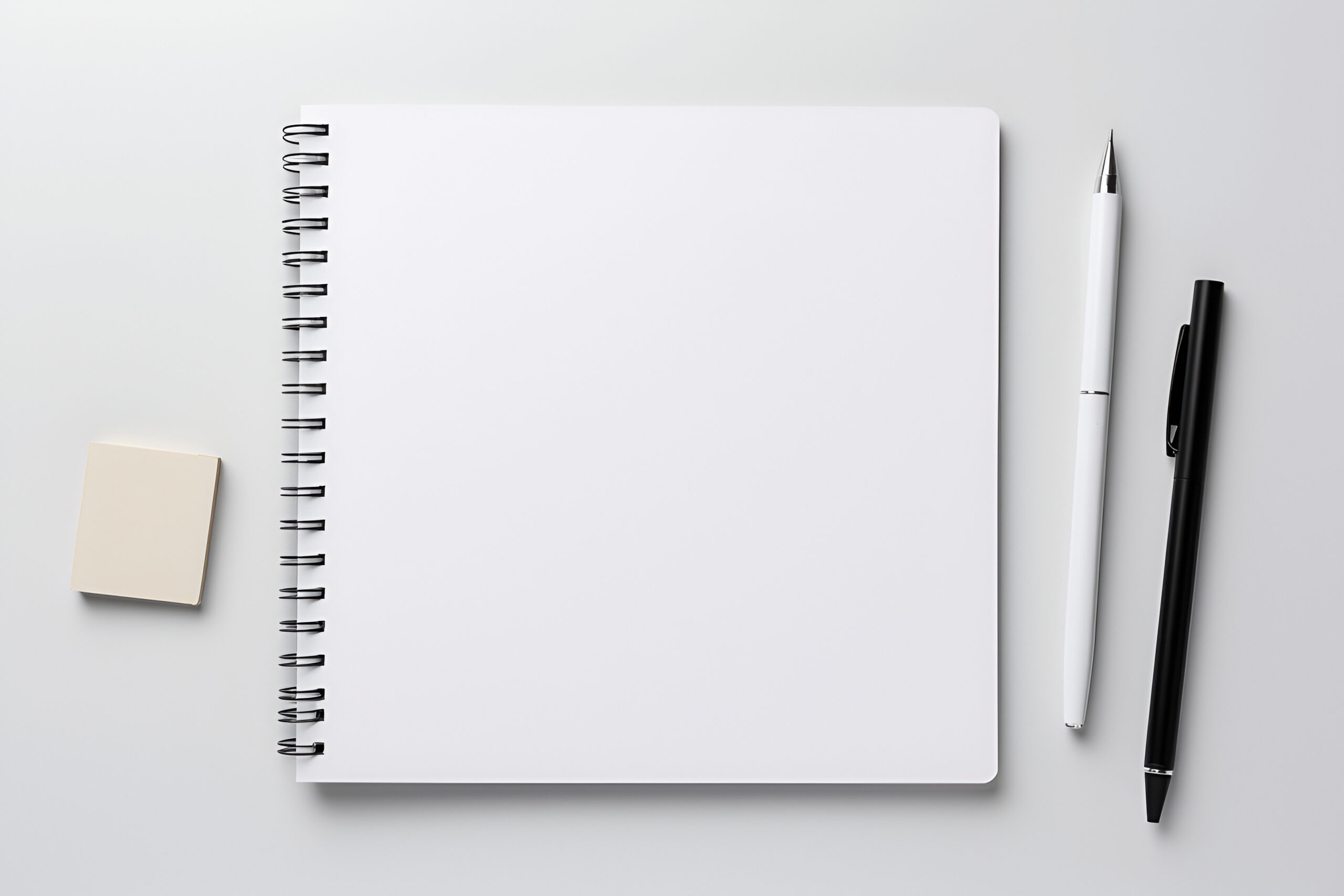
ここまで子どもの床矯正のメリット・デメリットについてお伝えしてきました。
子どもの床矯正の要点をまとめると以下のとおりです。
- 床矯正のデメリットは重度の歯並びには対応できない、適応できるタイミングが限られる、後戻りする可能性がある、などがあげられる
- 床矯正が向いている歯並びは、軽度の叢生、下顎前突、過蓋咬合がある
- 床矯正の失敗を防ぐためには、治療開始のタイミングを重視する、装着期間を守る、治療後の維持管理も重視することが挙げられる
お子さんの床矯正を価値あるものにするために、これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
